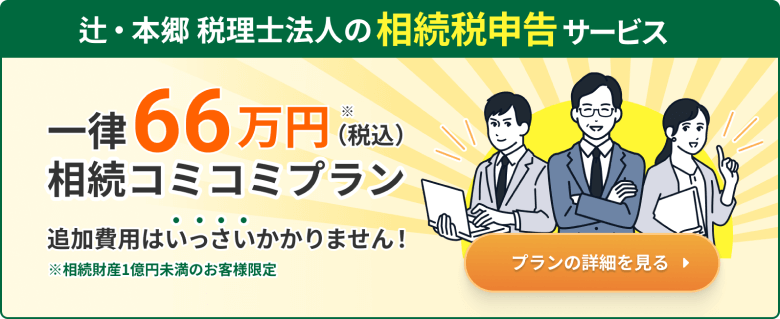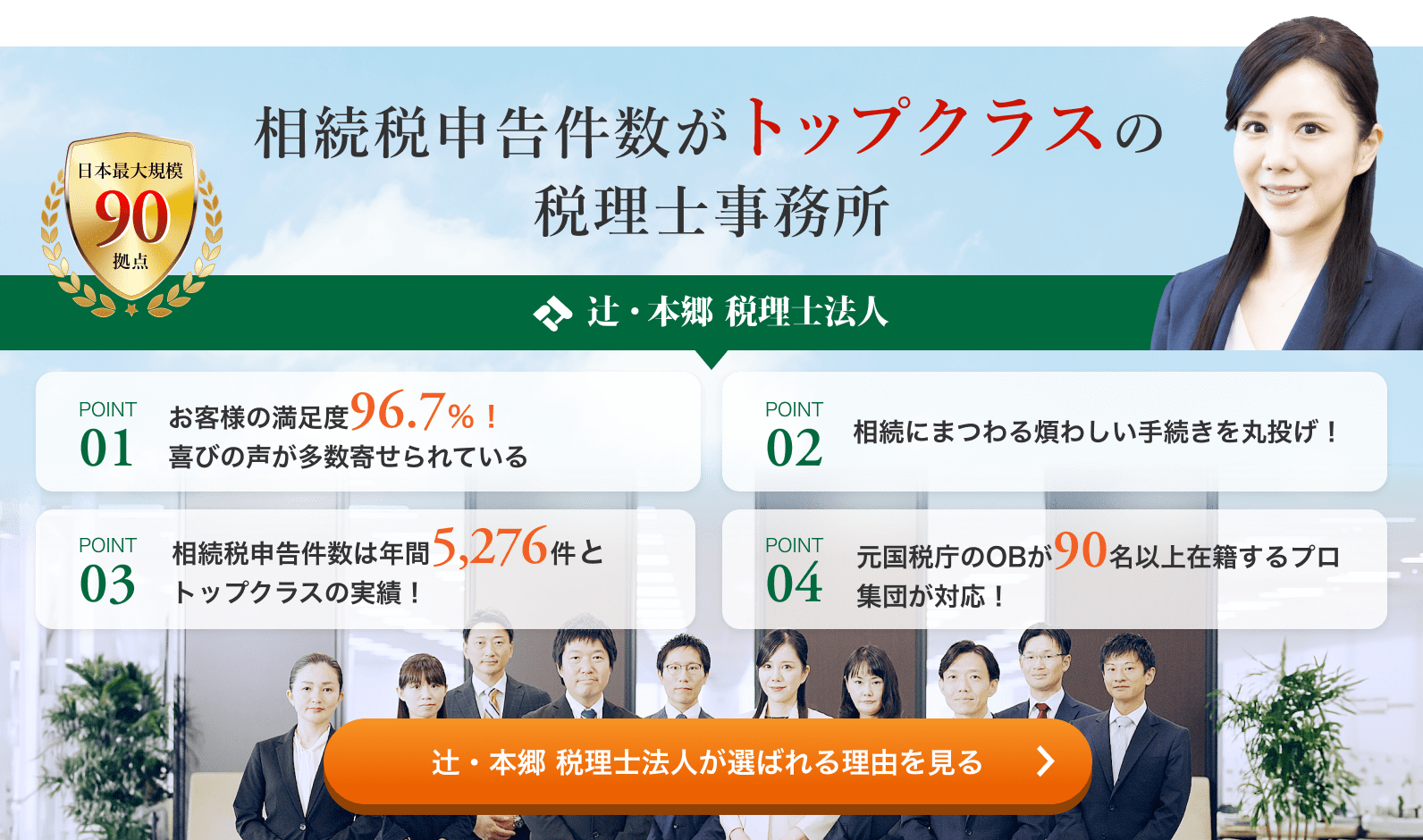被相続人の遺言により、遺産を相続できないまたは遺留分(いりゅうぶん)に満たない割合しか遺産を相続できない法定相続人が発生したときに、遺産を受け取った他の法定相続人等に対して、遺留分の権利を主張し請求を行うことが可能な場合があります。
この場合、その権利を請求した相続人および(遺産を相続した)請求された相続人等の税務手続きはどのようになるのでしょうか。
遺留分とは
被相続人(亡くなられた方)が遺言等で自分の財産を誰に相続させるのかを指定していた場合、指定されていない法定相続人が遺産を相続できない(または少額しか相続できない)ということが起こります。
例えば「すべての財産を血縁関係のない第三者へ遺贈(いぞう)する」と記した遺言書が見つかったとしたら、近親者は今後の生活が揺らぐことにもなりかねません。
民法では、相続人が一定の割合の遺産を受け取る権利があり、最低限度の生活の保障という観点から相続分として基本的な財産の配分割合が決まっています。
また、本来相続される財産のうち、最低限の相続分を回復する権利として遺留分を定めていますが、その権利者(遺留分権利者 いりゅうぶんけんりしゃ)は、配偶者または子(あるいは子の代襲相続人)、子がいない場合は直系尊属とされています。
遺産を相続できないまたは法定相続分の2分の1(遺留分)に満たない割合しか遺産を相続できない遺留分権利者は、遺産を相続した他の相続人等(受遺者 じゅいしゃ)に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭を請求する権利があります。
遺留分侵害額請求権
民法改正により、令和元年7月1日以降に開始する相続については、遺留分減殺(げんさい)請求権から遺留分侵害額請求権へと改正され、遺留分権利者の権利が金銭債権化にされたことにより、従来のように受遺者と遺留分権利者とで共有関係になることがなくなりました。
<民法改正前>

改正前は、遺留分権利者は物的請求権を持ち、遺贈財産のうち遺留分に満たない部分は、例えば不動産等について権利を主張し、登記名義等の持分を変更するように請求をする必要がありました。
そのため、受遺者と遺留分権利者で共有になる場合が多く、その後共有関係を解消させるためには、共有物分割手続きが必要でした。
<民法改正後>
改正後は、遺留分権利者の権利が金銭債権化されたため、遺留分権利者は、遺留分侵害額相当の金銭を請求できることになりました。
ただし、金銭で精算することが困難な場合、双方の合意があれば資産の移転により精算することも可能です。しかし、この場合は代物弁済によるものとして譲渡所得税が課税されることとなったため、注意が必要です。
相続税の申告期限
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日から10カ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署へ提出します。
相続税の申告時に遺留分侵害額請求に基づく金銭の額が確定していない場合には、遺留分侵害額請求がなかったものとして、各人の相続税の課税価格および相続税額を計算し申告することになります。
このように、遺留分侵害額請求権が行使されていても申告期限は延長しないことから、遺言の通りに相続(「遺贈」といいます)したとして相続税申告書を提出し、遺贈を受けた人がそれぞれ納税手続きを行います。
遺留分侵害額請求に基づく金銭の額が確定した場合
上記により期限内申告書を提出した後、遺留分侵害額請求に基づく金銭の額が確定したことにより、その申告に係る課税価格および税額が過大となったときは、その額が確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に、更正の請求(払い過ぎた税金を戻してもらう手続き)をすることができます。
一方、遺留分権利者は、更正または決定がされるまでは修正申告書または期限後申告書を提出することができます。
この場合、修正申告書または期限後申告書の提出日が相続税の納期限となりますので、申告書を提出する前に納税を済ませることにより延滞税は発生しません。
詳しくは、お近くの地域の辻・本郷 相続センターへご相談ください。